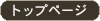|
キーワード: |
由旬 小由旬 大由旬 ヨージャナ クローシャ ダヌ ハスタ 拘盧舎 弓 肘 大唐西域記、法顕伝、遊行距離、アッタカター |
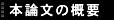
我々はできうれば釈尊の年譜を作成したいと考えている。そのためには、釈尊が成道後45年間にわたって行われた衆生教化のためのヒンドゥスタン平原各地の遊行がどのように行われたのかを明らかにすることは不可欠の研究課題である。ところで仏典では、釈尊の一日の遊行距離は1由旬(yojana)あるいは2由旬であったとされている。けれども1由旬が現代の長さの単位に換算してどれくらいの長さに相当するかが分からなければ、何の役にも立たないわけである。ところで1由旬の長さについては、従来の学説では4kmから23kmまでと区々さまざまであって、未だ定説が得られていない。本論はこの由旬の長さを、インドのさまざまな文献の記述や、『法顕伝』『西域記』などのインド旅行記、あるいは律蔵の規定などを材料として、厳密に検討したものである。以下には本論文の結論部分をほぼそのまま引用する。
[1]まず「由旬」という長さ(距離)を表す単位の持つ性格を検討しておこう。
[1-1]「由旬」は古代インドの長さを現す度量衡のユニットの最長の単位である。この単位の基礎には指(aṅgula,aṅguliparva)や搩手・指尺(vitasti)、肘(hasta)などがあった。「指」は人の指の幅であり、「搩手」は掌を拡げたときの親指の先から小指の先までの長さであって、12指が1搩手に相当する。そして「肘」は肘から掌の先までであり、2搩手が1肘に相当する(巻末の微細単位表を参照されたい)。そしてその上の単位が「弓(dhanu)」であるが、これは身長に等しく4肘が1弓に相当する。
しかし指の肉厚や肘から指先までの長さは人によって異なる。身長にしても同様である。このように個人差のあるものを標準化すると不都合をもたらす場合もあった。例えば常人よりも背の高い人の住まいを常人と同じ基準で作ると鴨居に頭をぶつけて危険であるから、こういう人の住まいは標準よりも大きめに作られるべきである。これが逸見梅栄のいう「相対的度量制=Mātrāṅga」である。もし特定の人をイメージした等身大の像を作るときには、「指」も「肘」もその人の大きさに合わせて作られた。
しかし度量衡の基準となるべき単位が人それぞれによって異なっては、度量衡としての役割を果たせないから、標準的な長さが決められたに相違ない。それが逸見梅栄のいう「絶対的度量制=Mānāṅga」である。例えば仏教の律蔵でいう'hasta'は'sugatavidatthi(仏搩手)'であるとされるが、これは等身大の仏像が丈六とされるように、常人の3倍である。しかしこれが仏教の律蔵の度量衡の基準として定められたのなら、尺度として十分に機能するわけである。
[1-2]このように由旬の下位の単位は人間の身体の各部を基礎として形成されていた。もちろんこれを度量衡として用いる場合は標準化がなされていたのであるが、しかし人間の体格は時代が進むにしたがって発達する傾向がある。例えば平均身長150cmの時の基準が、平均身長が170cmになったときにも同様に使われるとすると、鴨居に頭をぶつけることは常態となる。こうなると度量衡の単位としては不都合であるから、そこで「肘」や「弓」の長さは徐々に大きくなったと想像される。中国において「尺」や「歩」が徐々に大きくなったことは歴史的に証明されている。
[1-3]このように「肘」や「弓」という身体の各部を単位とするものは、比較的標準的スケールを作りやすかったであろうが、クローシャや由旬というような距離を表すような長さの単位になると、測量法の確立されていなかった時代には、そのスケールは作りにくかったであろう。例えば1由旬が10kmであると定められていたとしても、この10kmを正確に測量する技術がなければ、目分量なり感覚なりに頼らざるを得ないわけである。長い長さを表す単位が途端に、牛の声の聞こえる距離(krośa)とか、牛がくびきをつけて荷物を引く距離(yojana)という、いかにも感覚的な単位を表す名称になってしまうことがこれを雄弁に物語っている。
したがって由旬はもともと正確なものではなく体感的なものであった。今の文明社会におけるような度量衡の感覚を持ち込むことは危険であろう。
[1-4]しかしながら「律蔵」では明らかに由旬も客観的な距離を測る単位として認識されている。『パーリ律』の「捨堕016」の規程が、羊毛を担って3由旬を1歩でも越えると罪になるとするとすれば、これは絶対的な長さの単位として扱われていたのである。それを測量する技術がないとすれば、結果的にはそれは主観的なものにならざるを得ないものとなったとしても、意識的にはこの「3由旬」は絶対的度量衡の単位として扱われていたのである。
[2]「由旬」は以上のように、長さを表す度量衡の単位としての標準化されたスケールとしての性格を有していた。しかし一方では極めて便宜的に使われる場合もあった。あるいは体感的と言ってもよいかもしれないし、山勘的と言ってもよいかもしれない。
[2-1]インド仏蹟案内書に書かれている距離はあまり当てにならないのが普通である。例えばサヘート・マヘートに行かれた人は多いであろうが、祇園精舎であるとされるマヘートから、スダッタ長者の屋敷跡とされるサヘートの遺跡まで、正確に何メートルと言える人は少ないであろう。
法顕や玄奘を我々と同等に見るのはいかにも失礼であるとしても、彼らとて伊能忠敬が測量したような方法でインド全土を測量して回ったのではない。したがって彼らの記録に記された「由旬」と、度量衡における絶対的なスケールとしての「由旬」とを同列に置くのは危険である。客観的な距離の単位としての由旬の長さを検討しようとするとき、それらはあくまでも第二義的な資料にしかならないということである。
[2-2]しかし実際の旅は、地図に示された距離とは異なる。道中には河も山もあり、したがって道路も直線的には引かれていない。もちろん季節も天候も、本人の体調も影響してくるはずである。このような実地体験の上から体感的に得られた「由旬」も価値がないわけではない。特にこの論文の出発点が、釈尊の1日の遊行の長さを知りたいということであったとすれば、この利用価値は大きい。
[3]以上のような基本的な事柄を留意した上で、本論文の主題に結論を下すとすれば以下のようになろう。
[3-1]インドの距離を表す単位としての由旬には2つの種類があった。1由旬を4,000dhanuとする「小由旬」と、8,000dhanuとする「大由旬」である。前者はマガダにおいて、後者は北方インドにおいて用いられていた。これは1由旬を4krośaとするか8krośaとするか、あるいは1krośaを500dhanuとするか1,000dhanuとするかという単位の相違による。
[3-2]一方中国の唐時代にインドを旅行した玄奘や義浄の伝えるところによれば、当時のインドには「聖教所載の由旬」すなわち「内教の由旬」と、「インド国俗の由旬」すなわち「西国俗法の由旬」の2種類が行われていた。この2つは前項の「小由旬」と「大由旬」の関係のように2倍の関係ではないがそれに近い。おそらく「聖教所載の由旬」「内教の由旬」とは「律蔵中に規定された由旬」のことであって、「マガダ」で用いられていた「小由旬」に相応し、「インド国俗の由旬」「西国俗法の由旬」は当時のインドで一般的に用いられていたもので、「北方インド」で用いられていた「大由旬」に相応するものと考えられる。「聖教」「内教」を「マガダ」に結びつけることには必然性があるであろう。
何故このような2種類の度量衡ユニットができ上がったのかは判らない。時代が下るにしたがって人の体格がよくなり、それにしたがって長くなったという理由もありそうであるが、しかし体格が2倍になったということは考えられないし、そもそも人の体格を基礎とするdhanuやhastaの長さは変化していないようであるから、この理由には蓋然性がない。
しかし「律蔵」の規定の中に組み込まれた「由旬」は、それが罰則を持つ法律文書であったがゆえに、容易に変更できなかったであろう。したがって「小由旬」が古い時代の由旬の長さを伝えたものであるとは言いうるであろう。
[3-3]上記のような度量衡の長さ(距離)を表す単位としての「小由旬」は約6.5kmに相当し、「大由旬」は約13kmに相当する。これは古代のインド人の体格や中国唐時代の「里」との関連などから導き出されたものである。また「小由旬」の約6.5kmは「律蔵」の規定に当て嵌めて検証しても齟齬は見いだされない。
[4]法顕や玄奘などの旅行記、およびpāḷiの原始聖典やそのaṭṭhakathāなどの記述から分析した結果の体感距離としての1由旬は約11.5kmに相当する。これらはインド国俗の「由旬」を念頭に置いたものであろうから、本来は「大由旬」と等しくなるべきものであるが、これが1.5kmほど短くなっているのは、重い荷を背負うて旅する旅行者にとっては、距離が長く感じられる傾向は免れがたく、これが反映されたものであろう。また道中には山や河があり、雨も降れば風も吹くから、現実的には直線的な単位としての「由旬」よりも短い距離が、1由旬と感じられたのである。
われわれは釈尊の遊行の速度を知ろうとしてこの検証を始めたのであるから、この結果も無視するわけにはいかない。そういう意味では釈尊の遊行の距離が1日平均1由旬であったとすれば、釈尊は1日に平均約11.5km歩かれたわけであり、王舎城からガンジス河沿いのルートを通って舎衛城に行かれたとするなら約650kmほどになるから、これには56.5日ほどを要したことになる。我々の見解によれば、釈尊が遊行に費やすことのできる期間は、古代の中国暦でいえば11月中旬頃から翌年の2月中旬頃まで、現代の暦では2月の初め頃から4月の終わり頃までの約3ヶ月間であって、その間に王舎城から舎衛城の往復はできなかったということになる。